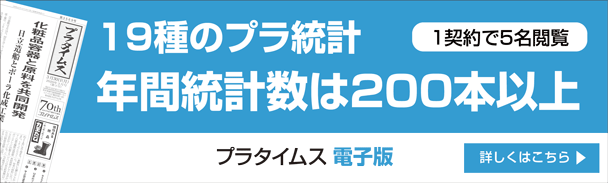理化学研究所創発物性科学研究センター強相関物質研究グループの中村大輔上級研究員、田口康二郎グループディレクター(最先端研究プラットフォーム連携事業本部強相関材料環境デバイス研究チーム副チームディレクター)、強相関理論研究グループの永長直人グループディレクター(最先端研究プラットフォーム連携事業本部基礎量子科学研究プログラムディレクター)、早稲田大学理工学術院先進理工学部の望月維人教授、リー・ムークン講師らの共同研究グループは7月3日、キラル構造口を持つ磁性体の抵抗が室温で電流方向に依存して変化することを発見したことを発表した。
本研究成果は、スピンと電子の相関を利用した情報制御に向けた基盤技術の発展に貢献すると期待される。
共同研究グループは、電流と電圧が単純な比例関係にない「非線形電荷輸送現象」の中でも整流効果をもたらす「非相反出電荷輸送」が期待される、キラル構造を持つ磁性体「CosZneMns(コバルト・亜鉛・マンガンの合金)」に着目し、室温を含む幅広い温度領域で非相反電荷輸送現象を観測することに成功した。さらに、異なる温度・磁場の条件下で生じた、2種類の非相反電荷輸送現象を分離することにも成功した。この二つの現象を理論解析することで、キラル構造を持つ磁性体における非相反電荷輸送現象は、ニつのスピン(電子の「自転」)間の相対角度の大きさに依存するスピン散乱と、円錐状のスピン配列に伴う電子の非対称なエネルギー状態という2種類の要因によって発現していることが明らかになった。
これにより、キラルな構造を持つ磁性体がもたらす非相反電荷輸送現象を応用するための下地となる物理現象の深い理解が得られた。
単一の材料だけで生じる非線形な電荷輸送現象に関する理論を深化させたことは、より小型でエネルギー効率の良い電子デバイスの開発につながる基盤技術となる可能性がある。カーボンニュートラル社会の実現といった社会的課題の解決にも貢献することが期待される。
物理学の基礎研究は封来的な技術革新の源泉となる可能性を秘めている。
本研究で得られた知見は、スピンと電子の相関を利用した新たな情報制御技術、およびスピンの不揮発性や高速操作性を利用した次世代のスピントロニクスデバイスの開発の可能性を開くものであり、科学と産業の境界を超えた価値創造につながることが期待される。
本研究は、科学雑誌『ScfenceAdvaoces』オンライン版に掲載された。