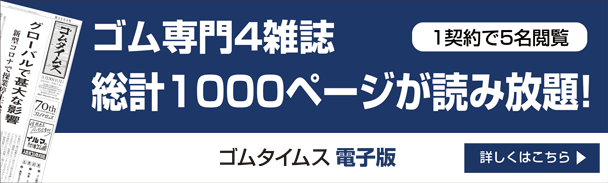経済産業省・国土交通省が主導する「フィジカルインターネット実現会議」内に設置されている「化学品ワーキンググループ」は、2025年度フィジカルインターネット実現会議において、2030年を見据えた持続可能な物流構築に向けた2025年度の活動方針を報告した。
「化学品ワーキンググループ」には、現在、荷主事業者、物流事業者を中心とする81企業・1大学、日本化学工業協会、石油化学工業協会、経済産業省・国土交通省の関連各部署等が参加しており、同社は、三井化学、東ソーおよび東レとともに事務局を務めている。
化学品WGは2023年6月に設置承認後、約2年間が経過し、参画企業も当初の44企業から81企業に拡大した。その間、2023年12月に「物流の2024年問題」に対する自主行動計画を発表、2024年12月に共同物流の実証実験(DXを用いた共同物流プラットフォーム)の効果を発表している。
これらの実績を踏まえ、2025年度は「物流の2024年問題」に対する取組をさらに推進するために、「商慣行の見直し」と「物流DXの推進」の2項目を重点施策として進める。
商慣行の見直しについては以下の項目を重点テーマとして取り組んでいく。
2025年4月施行の物流総合効率化法(正式名称「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」)に対応し、予約受付システム導入など参画各社での対応を強化し、物流総合効率化法の本格施行(2026年4月)に対応し、車上受け・車上渡しの徹底、附帯作業の削減を取引先業界団体へ要請する。
荷役作業時の安全対策について、リーフレットを作成し、取引先業界団体、並びに着荷主に対して協力を要請し、社内輸送、ストックポイント転送についてパレタイズを進めることに加えて、納入時のパレタイズについては着荷主の理解を促すために業界内外へ発信する。
共同物流について、輸送モード別やエリア別の各分科会で検討している取組を具体化、鉄道輸送分科会では31ftコンテナによる共同往復輸送のテストを実施予定となる。
2024年に実施した実証実験の結果、標準コード・メッセージによるデジタルコミュニケーションが複数の荷主と物流事業者間の共同物流に有効であることを確認できたため、その後続作業として共同物流プロセス標準化の検討、メッセージ・コード標準化の検討、DXの実装に向けた調査研究の取り組みに着手している。
これらの作業により、化学品の情報標準ガイドラインを策定するとともに、2026年度以降のデジタル化実装に向けた計画を策定する。また、昨年の実証実験でも実施した物流実績データによる貨物動態可視化については、危険物有姿品の全国貨物動態可視化に展開する方向で進めている。
化学品WGは関係省庁、業界団体等と連携しながら、フィジカルインターネットの実現に貢献していく。
2025年06月27日