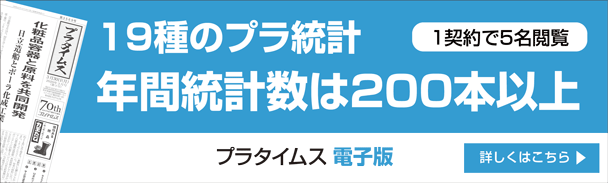*この記事はゴム・プラスチックの技術専門季刊誌「ポリマーTECH」に掲載されました。
*記事で使用している図・表はPDFで確認できます。
シリーズ連載② 現場に役立つゴムの試験機入門講座
第3回 加硫試験機 (Curemeter)─ その2
蓮見―RCT代表 蓮見正武
前回、密閉型ねじり振動式加硫試験機について解説しましたが、最近の加硫試験機は非常に高精度高機能になっています。今回はそのような加硫試験機の応用事例を紹介します。
なお、前回同様JSRトレーディング(JSR)、アルファテクノロジース(α-TECH)、東洋精機製作所(東洋精機)と略称します。
加硫試験機(キュアメーター)の応用
1.発泡測定
発泡ゴム(スポンジゴム)の配合、製造は高度な技術と経験が必要です。ゴム技術の大先輩である金子秀男氏は「応用ゴム化学12講」の中で「スポンジゴムは科学というよりも職人芸に近い」と述べており、スポンジゴムについては
1.発泡以前に加硫が進むと、ゴムが硬くなってうまく膨れてくれない。
2.発泡がうまく行っても加硫が進まないと、ガスが逃げ、せっかくの泡もつぶれる。
3.発泡と加硫がうまく進んでも、泡が大きくなると熱の伝わり方が遅くなる。加硫が遅れやすくなる。
4.高温短時間の発泡加硫ほど収縮が大きい。
5.素練りや熟成によって発泡度が著しく変化する。
とスポンジの難しさを述べています3)。
スポンジゴムは加硫と発泡のバランスと言われていますが、加硫試験機に発泡圧力測定機能を組み込み、加硫の進行と発泡圧を同時に測定できるものがあります。
上島製作所FDR VR-3111を例にとると、下ダイ(検出側ダイ)にトルク検出センサーと別にダイにかかる圧力を検知するセンサーを設け、発泡によりダイを押し開こうとする力を検知します。
VR-3111でスポンジゴムの加硫と発泡圧を同時に測定した例を図2に示します。
加硫トルク、発泡圧力とそれぞれの微分(時間当たりの変化)を表示しています。
スポンジの加硫条件の設定はベテラン技術者が配合処方、加硫温度、仕込量を色々変えて発泡テストを行っていました。この作業は労力と時間がかかります。発泡付き加硫試験機を用いれば大幅に負担を減らすことが可能です。また、製造工程の管理に用いればスポンジ製品の品質安定に役立ちます。
J. S. Dick氏とR. A. Annicelli氏は、発泡付き加硫試験機MDR-Pを用いて発泡剤と発泡活性剤、加硫系の配合について検討を加え貴重な結果を得ています4)。ポリマーダイジェスト誌2001年12号に翻訳が掲載されているので、発泡ゴムに携わる技術者はお読みになることを薦めます。
2.粘弾性について
近代的な加硫試験機は密閉型ローターレスねじり振動方式が採用されています。通常駆動側ダイに100cpm、±1゜または±0.5゜のねじり振動を与え、相手側ダイに伝わるトルクを検出しPCで記録解析しています。
加硫していないゴムは塑性が大きく軟らかいので加硫トルクは小さく、加硫するにしたがってゴムは硬くなり弾性が増加して塑性が減少する結果、加硫トルクが大きくなります。この加硫トルクは弾性と塑性が複合されているので複素弾性トルクと呼ばれます。
PCを装備したキュアメーターはPCによって加硫トルクを弾性トルク(Ḿ)と粘性トルク(Ḿ́)に分離します。複素弾性トルクはM*で表されます。
(iは虚数項を表す)
駆動側ダイに正弦波(サインカーブ)の振動を与え、検出側ダイに伝わる振動はやはりサインカーブとなり、Ḿ、Ḿ́もサインカーブですがḾとḾ́は位相が90゜ずれています。サインカーブなので位相により+の値と-の値をとり、不便なので
により絶対値にします。
Ḿ、Ḿ́の値は配合で変化するだけでなく加硫の進行に伴って変化することにより絶対値ではなくその比である
で表現することが多く行われます。
tanδはタイヤの発熱性やスリップ性、防振ゴムの振動吸収など動的特性と深く関わる特性です。
一般に未加硫ゴムはtanδ≒1、加硫ゴムはtanδ≒0.1程度の値をとります。
ムーニー粘度計によるムーニー緩和がゴム加工性のパラメーターであるように、加硫曲線の粘性トルクḾ́も加工性との関連が示されています。
図4はCIS含量の異なる2種類のポリイソプレンを比較したとき、弾性トルクḾの曲線はほとんど同じであるのに粘性トルクḾ́は大きく異なっているので、加硫開始までの挙動、例えば射出成型時のゴムの流動性に差があることが予想されます。
3.超低粘度ゴムの加硫試験
シーラント・タイヤ、セルフリペアリング・タイヤなどと呼ばれるタイヤがあります。シーラントという特殊な材質がタイヤ内面に貼ってあり、タイヤが釘踏みしたときに空気が漏れることを防ぎます。シーラントは非常に低粘度、低硬度で通常に加硫試験しても、ほとんどトルクが上がらず加硫曲線を描くことができませんでした。しかし、近代的な加硫試験機はPCによってスケールを拡大し、加硫曲線を平滑化処理することができるため、このような超軟質材料の加硫挙動も測定することができます。
図5に一例を示します。
左図はトルクスケールが通常のゴムと同じ2.0N-mの場合で、ほとんどトルクが上がっていませんが、右図はトルクスケールを0.05 N-mにアップしたところ明瞭な加硫曲線が得られ、tc(10)、tc(90)の加硫パラメーターを求めることもできました。