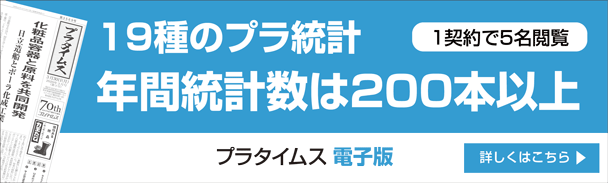WWFジャパンが事務局を務める国際プラスチック条約企業連合は6月27日、同日に、国際プラスチック条約を、法的拘束力のある調和の取れたルールを基盤とすることが経済活動にも有益であることを示す新たな分析結果を発表した。
同分析は、2025年8月5日~14日に、スイス・ジュネーブで開催予定のプラスチック汚染根絶のための国際条約の制定に向けた最終の交渉会議(政府間交渉委員会第5回会合第2部、INCー5・2)に先立って、6月初旬に、「国際プラスチック条約企業連合(Business Coalition for a Global Plastics Treaty)」が公開した英語版を日本向けに紹介したもの。
企業連合がSYSTEMIQ社に委託し、条約の主要な条項(3条・プラスチック製品/化学物質規制、5条・製品設計、8条・廃棄物管理/EPR(拡大生産者責任))が、各国で分散したルールとなる場合と、調和の取れたルールに基づく場合との経済的合理性を比較分析している。特に、交渉会合でその動向が鍵となるとされる6ヵ国(日本、ブラジル、中国、インド、インドネシア、南アフリカ)についての分析を深掘りしている。法的拘束力のある調和の取れたルールに基づく条約が経済活動にも有益であることが定量的に示された。
同分析結果の要旨は、製品・化学物質規制(3条)、製品設計基準(5条)、廃棄物管理・EPR(8条)に国際ルールを導入することで、分散ルールの場合と比べ、水平リサイクルによる再生素材を、2040年に、世界で77%、日本で90%増やすことができ、同様に国際ルールを導入することで、分散ルールの場合と比べ、問題ある使い捨てプラスチックを2040年までの累積で、世界で2・22倍、日本では2・25倍削減できる。
しかも、国際ルールを導入することは、著しい経済効果をもたらす。国際ルールの下で、世界のプラスチックバリューチェーンの経済活動は2040年に2025年比で31%増大。日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランド全体でも7%増大する見込みとなる。
2025年07月01日