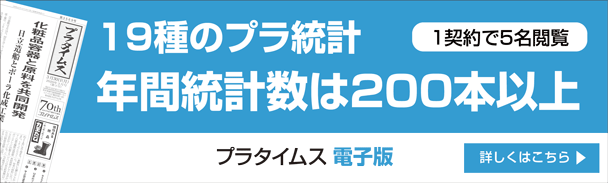*この記事はゴム・プラスチックの技術専門季刊誌「ポリマーTECH」に掲載されました。
*記事で使用している図・表はPDFで確認できます。
特集1 ゴム用添加剤における製品への活用
ゴム用合成可塑剤の理論と実践
㈱ADEKA 仙石忠士
1.はじめに1)
ゴム製品には原料ゴムの特性を最大限に引き出すため、多くの配合剤が添加されている。自動車用部材や工業用分野においては、長寿命化・高性能化のため、耐熱性、耐油性などの特性に優れた特殊ゴムが使用されている。特殊ゴムは、アクリロニトリルブタジエンゴム(NBR)、アクリルゴム(ACM)など極性の強いものが多く、共通する課題は低温柔軟性である。自動車用部材にはマイナス40ºCの脆化温度を要求される場合が多い。極性ゴム自身の耐寒特性だけでは不十分なため、「可塑剤(軟化剤)」に頼るところが大きい。一般的にゴムやポリマーとの相溶性が良好な可塑剤であれば、添加量とともに耐寒性は改良される。ただし、可塑剤の添加により最終製品が実際に使用される環境下において、原料ゴムが本来持っている特性が損なわれないことが前提となる。あらゆる特性を兼ね備えた万能な可塑剤は存在しない。したがって、最終製品の使用目的に対して原料ゴムだけではなく、可塑剤の特性も考慮した可塑剤の選択が必要となる。
1.1 合成可塑剤の種類と特長
主な合成可塑剤を構造別に分類し、代表的なグレードを表1に示す。
合成可塑剤は極性ゴム(樹脂)との相溶性を考慮し、強極性のエステル基を活用して設計された化合物である。以下に合成可塑剤(以降、可塑剤と表記)の構造別にその特長について説明する。
1.1.1 フタル酸エステル
世界中で最も多く使用されている汎用可塑剤であり、DOP(ジ2-エチルヘキシルフタレート)が代表的である。構造に芳香環を持ち、各種ゴムへの相溶性が良好である点、安価である点が特長である。一方、耐熱性はやや劣り、耐寒性改良効果は小さい。耐熱性が要求される特殊ゴム用にはあまり適さず、使用上限温度100ºC以下の用途に限定される。
1.1.2 脂肪族二塩基酸エステル
DOA(ジ2-エチルヘキシルアジペート)、DOS(ジ2-エチルヘキシルセバケート)が代表的である。可塑剤自身の極性が弱いため比較的極性の弱いゴムと相溶しやすい。低温特性が非常に優れるのが特長である。ただし、耐熱性が劣るためDOAは使用上限温度100ºC以下、DOSは同120ºC以下の用途に限定される。特殊ゴム用としては、DOSがクロロプレンゴム(CR)に使用される。
1.1.3 芳香族多価カルボン酸エステル
構造に芳香環を持ち、トリメリット酸エステルが代表的である。フタル酸エステルよりも高分子量であり、耐揮発性(耐熱性)が非常に優れているのが特長。150ºC以上の耐熱性が要求される用途に適しており、ピロメリット酸エステルは175ºCにおいても安定である。ただし、一般的に耐寒性改良効果の小さいものが多く、低温特性が重視される用途には適さない。
1.1.4 エーテルエステル
強極性のエーテル結合を活用して設計された可塑剤であり、極性ゴムに相溶しやすい。上述の脂肪族二塩基酸エステルに匹敵する耐寒性改良効果を持っているのが特長である。高分子量タイプの化合物は、耐熱性も兼ね備えており、各種特殊ゴム用可塑剤として最も多く使用される。中でもアデカサイザー RS-107は低~高ニトリルのNBRに相溶し、標準的可塑剤として適している。
1.1.5 ポリエステル
二塩基酸(アジピン酸が主流)とグリコールの繰り返し単位を構造に持ったオリゴマー体で平均分子量1,000~3,000のものが多い。高分子量のため、燃料油などで抽出されにくく、耐揮発性も良好なのが特長である。高分子量グレードは耐抽出性に優れる反面、耐寒性は劣る。また、一般的に相溶性に劣る傾向があるため添加量にも注意が必要である。
1.2 可塑剤選択のポイント
可塑剤に要求される基本的な特性は、(1)ゴムとの相溶性およびゴムへの保留性が良好なこと、(2)可塑化効果に優れること、(3)化学的に安定であることである。これらの基本特性に加え、最終製品の使用環境下に応じて、耐熱性、耐寒性、耐油性などの性能も必要となる。これら複数の性能を全て満足させることは難しく、性能バランスを考慮した可塑剤選択が必要となる。以下に可塑剤選択のポイントについて説明する。
1.2.1 相溶性
可塑剤を選択するにあたり最も重要なのは、ゴムとの相溶性である。各種ゴムに対する相溶性は、溶解度指数(以後SP値)を用いると予測しやすい。SP値は樹脂や可塑剤の極性を数値化した尺度であり、数値が大きいほど極性が強いことを表している。表2に主な特殊ゴムと可塑剤のSP値対比を示す。
数値の近いもの同士ほど相溶しやすいと考えるので、可塑剤の選択肢をある程度絞り込むことが可能である。
1.2.2 耐寒性
対象ゴムに対する相溶性の判断ができたところで、次に要求性能について考える。可塑剤を必要とするゴムに共通する性能課題は低温特性(耐寒性)である場合が多い。例えば、自動車関連部品の場合、脆化温度としてマイナス40ºCが要求される。NR、SBR、BRなどの汎用ゴムは、原料ゴム自身が十分な耐寒性を持っており、耐寒付与目的として可塑剤の必要性はない。他方、EPDMを除く特殊ゴムは、耐熱性や耐油性を付与するため強極性に設計されている。そのため結晶性が強くなり、柔軟性に乏しく耐寒性に劣るものが多い。耐寒性を改善するためには可塑剤に頼らざるを得ないのが実状である。図1にNBRにおけるDOPおよびエーテルエステル系可塑剤の添加量による耐寒性改良効果を示す。
一般的に可塑剤を増量することにより耐寒性は改良される。図1を例にとると、DOPにて脆化温度マイナス40ºCをクリアするためには、エーテルエステル系可塑剤の約2倍近くの添加量が必要となる。このように可塑剤の構造により効果は異なり、耐寒性を効果的に付与するためには、分子運動しやすく、結晶化しにくい構造を持つものを選択するとよい。具体的には、主鎖にエーテル結合や二重結合を持つものが良好であり、芳香環やエステル基を多く持つものは劣る傾向がある。
1.2.3 耐熱性
ゴム製品に添加した可塑剤が使用環境下にて揮発すると硬度上昇による柔軟性低下、物性低下、体積縮小などを引き起こす。その結果、ゴム本来の性能を失うことになり、耐寒性改良のために添加した意味がなくなってしまう。したがって、可塑剤は原料ゴムと同等以上の耐熱性を持つものを選択する必要がある。
表3に主な原料ゴムと可塑剤の使用上限温度を示す。
構造中に、芳香環を持つもの、アルキル基の分岐が少ないものが良好であり、主鎖にエーテル結合や二重結合を持つものは劣る傾向がある。また、揮発性の面から高分子量のものほど良好である。
1.2.4 耐油性
耐油性が必要とされる用途には強極性のゴムが使用される。これらは各種燃料油による膨潤を小さくするように設計されたものが多い。前述の通り、可塑剤は耐寒性改良目的で添加している場合が多いため、耐寒性保持の観点からもゴムから抽出されにくいものを選択する必要がある。具体的には、高分子量のもの、親水性のエーテル結合や水酸基を持つ構造のものが良好である。ポリエステル系可塑剤は高分子量のものほど耐油性が良好であるが、相反して耐寒性は劣るため、抽出量の許容範囲内にて他の可塑剤と併用される場合もある。
2. 各種ゴムに対する可塑剤選択2)
前述1での概論を踏まえ、個別の特殊ゴムに対する可塑剤選択例に